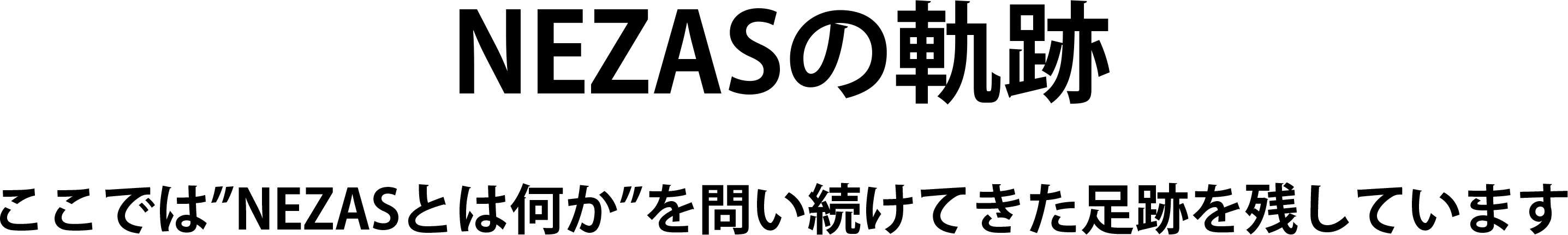
“NEZAS”は地域に根ざすことを掲げて名付けられました。ただ、それは単に根を伸ばすとか定着するという意味だけにとどまりません。
むしろ、地域とともにどうあるべきか、人々とともにどうあるべきか、そして人は人とどう向き合うべきか。その答えを追い求めるために動き続けることにこそ、NEZASの真の意味があると考えます。
第3回のゲストは、多様な分野の研究者どうしの対話の場づくりを行なっている、京都大学の宮野公樹先生です。今話題になっている、ご著書『問いの立て方』(ちくま新書)は、とことん問いを掘り下げていくことの大切さが説かれています。今回は、宮野先生との対話を通じて、そもそも問いとは何かから探求してみます。

主宰:新井将能
協力:PHP研究所『PHP』編集部
構成:社納葉子
写真:武甕育子
株式会社NEZASホールディングス代表取締役社長。栃木県出身。東洋大学大学院経営学研究科、社会学研究科修了。早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得。経営学修士、社会心理学修士。事業構想大学院大学にて客員教授も務める。
京都大学学際融合教育研究推進センター准教授。国際高等研究所客員研究員。学問論、大学論(かつては金属組織学、ナノテクノロジー)。立命館大学卒業後、McMaster大学、立命館大学、九州大学を経て2011年より現職。著書に『学問からの手紙』(小学館)、『問いの立て方』(ちくま新書)などがある。
新井 : 地域に根ざすことを目指す企業群でありたいという想いから、私はNEZAS(ねざす)という社名を選びました。最初は良いネーミングだと何の疑いもなかったのですが、次第に「そもそも根ざすとはどういうことなのか」と疑問を抱くようになりました。この自らの問いを探求していきたいと思う一方で、「そもそもこれは何のための『問い』なのか」「なぜこの『問い』に関心を持つに至ったのか」と思い巡らせるようにもなり、そんな時に書店で『問いの立て方』に出会いました。
平易な言葉で書かれているので読み易そうな印象を持ったのですが、いざ読み始めるとなかなか読み進めないことに気が付き、何度も行ったり来たりしながら時間をかけて読みました。
先生は以前から「問いの立て方」というテーマに関心がおありだったのでしょうか。
宮野 : 問いの立て方について真正面から書いて欲しいという編集者からの依頼があり、書いたものです。問いの「立て方」について真剣かつ誠実に考えると、どうしても、「問いとは何か」から論じる必要がある。その結果、お読み頂いたのでお分かりかと思いますが、ハウトゥではなくむしろ哲学の本になってしまいました(笑)。タイトルと真逆の内容で、読者に迷惑をかけるなと少し悩みましたが、そもそも、HOWを真っ当に考えたら必ずWHATやWHYになる、そういうことも伝えたくて、このタイトルのままにしました。
世の中には様々な専門や業種がありますが、一番大切なこと、大事なこと、本当のこと……、それらを突き詰めれば行き着くところは同じです。これこそが学問あるいは哲学と呼ばれる考え方でして、今回の『問いの立て方』も、そういうそもそも論から考えたというわけです。
新井 : 元々はいわゆる科学の研究者だったのに、現在のような人文系にかわられたきっかけは、何かおありだったのでしょうか。
宮野 : まだ金属組織学の研究者で、九州大学から京都大学に移った時には恥ずかしながら「研究で一発当ててやろう」と思っていました。ところがひょんなことから京都大学総長補佐や文科省学術調査官の仕事をすることになり、これまでとは見える世界が大きく変わりました。研究者の時は「僕の研究」が主語ですが、総長補佐の時は「大学」、そして文科省では「国」が主語になる。そういう体験を通じ、僕は徹底的にアンラーニング(これまで学んできた知識をリセットし、新しく学び直すこと)されたんですよね。「ああ、俺はなんと狭い世界にいたのか」といった具合に。それがあらゆることに対して「そもそも論」を考えるきっかけとなって、今のような、学問とは何か、大学とは何か、といった問いを持ったわけです。

新井 : ご著書の中で「問いは言葉によって表現される」と述べられています。私は、話している時に頭の中でイメージしていることが言葉でどの程度表せているのかについて関心を持っています。相手の反応を見て、どうしてこのような反応になるのか、使う言葉が適切ではなかったのか等しばしば考えます。
そのため、考えや問いとは言葉として表せたものがすべてなのか、頭の中でイメージしていても言葉で表せていないものも含まれるのか、そもそも頭の中でイメージしているものが考えや問いなのかという問いにもなってきます。
宮野 : それ自体がすばらしい「問い」です。まず、間違いなく言葉以前のものはあると考えます。たとえば「赤いリンゴ」と言った時、同じ「赤」でも思い浮かべる赤は人によって違います。つまり、言葉にした時点でどうしても限定的になるということです。さらに言えば、民族、国、時代等によって同じ言葉でも意味合いが違うことは、当たり前のことです。とは言え、言葉なくして考えることはできませんし、言葉とは、まあ、実に不便なものなのです。
では言葉以前のものは何かというと、例えば、マルセル・プルーストは、自身の小説でそれを「印象」と表現しています。ちなみに、暗黙知という言葉もありますが、これは、今日、「単に言語化できない知」のように使用されていますが、本来、マイケル・ポランニーが言いたかったことは、プルーストの印象に近いもの。すなわち、考えることそのものの過程について考察したものです。
僕が言いたいのは、間違いなく言葉以前のものもある。しかし、僕らは決して言葉の世界から抜け出せないということ。ただし、その言葉の世界は宇宙並みに広いですけどね(笑)。
新井 : 私が「問いとは何か」という問いと同様に関心を持ったのが「いい問いとは何か」という「問い」です。そもそも問いの主体が「いい問いだ」「本質的な問いだ」と自覚できるものなのか気になったのですが、宮野さんはどのようにお考えでしょうか。
宮野 : 自分が「これだ!」と思っても、一方で「ほんとうにこれなのか?」と絶えず疑い続けることが「いい問い」に繋がるのだと考えます。「いい」とは何か、そもそも「問い」とは何か……、果ての果てまで考えるとまるで地面がぐらりと揺れて地の底まで沈み込んでいくような感覚に襲われますが、ハイデガー曰く、「それでも一歩踏み出す」。これが、きっと「ほんとうの問い」なのでしょう。僕はそれを「本分」と言っています。
いやぁ、僕らの考える営み、生きる営みとは恐ろしいものですね。その恐ろしさへの驚きや畏怖は、「存在すること」の不思議と言えるでしょうね。学問であれ、ビジネスであれ、なんであれ、この存在の驚きから立ち上げられたものは、ちょっとやそっとでは動じやしないでしょう。

新井 : 人と人とが向き合う際にわかり合える状態があるとするならば、それぞれが自分自身を疑い続ける心を持ち合わせているかどうかによるのではないかと私は考えています。言い換えれば、自分自身を疑う心が相手を受容することに結果的に繋がるように思うのです。
宮野 : おっしゃる通りです。僕は「構え」という言葉をよく使います。「俺はまだまだだ。お前もそう思っているのか。よし、じゃあ話そうか」と、絶えず自分を疑い、それをさらけ出す。そこから対話が始まるのだと思います。
新井 : 先生はいい問いを見つけるためには違和感を持ち、違和感を持つことは自分を持つことだと指摘されています。もし違和感を持たない状況があるとすると、自分を持っていない状況が存在するのではと考えたのですが、いかがでしょうか。
宮野 : 違和感の発生は、やはり言語以前の問題ですから言語化できない。だからと言って言語以前の「印象」の方が正しいのかというと、そうとも限りません。新井さんが言われる状態は、なんとか純粋に自分の心の動きを見つめようとされているのでしょう。誰一人として自分の世界から一歩も抜け出すことはできないけれど、それを自覚し、考えを考える行為をやめない。学問とは、自分の内にもう一つの自分を見つめる目を持つことであり、新井さんのその問い続ける姿勢はほんとうに素晴らしいです。
(了)